『19番目のカルテ 徳重晃の問診』は、富士屋カツヒト原作による医療漫画で、今話題のTBS日曜劇場ドラマとして実写化されます。
主演の松本潤が演じる徳重医師は、あらゆる科を横断する“総合診療医”という新しい存在。専門医では拾いきれない患者の声に寄り添い、本質的な治療を追求します。
この記事では、ドラマ『19番目のカルテ』が原作の世界観をどのように再現し、どんな見どころがあるのかを詳しく解説します。原作ファンも、医療ドラマ好きも必見です!
この記事を読むとわかること
- ドラマ『19番目のカルテ』と原作漫画の違いと魅力
- 主演・松本潤と小芝風花のリアルな医療演技
- 原作者・富士屋カツヒトの実写化への思いと舞台裏
ドラマ『19番目のカルテ』が原作ファンに響く理由とは?
2025年7月からTBS系日曜劇場枠で放送がスタートする『19番目のカルテ』。
医療漫画の名作として名高い富士屋カツヒト原作『徳重晃の問診』を基に、主演・松本潤の熱演で実写化されました。
原作ファンが最も気になるのは、漫画で描かれた医師の哲学や患者との向き合い方が、どこまで丁寧に再現されているかという点です。
総合診療医という「第19の専門科」の魅力
ドラマタイトルの「19番目」は、既存の18の専門科に加え、患者全体を診る総合診療医という新たな存在を象徴しています。
“何科でもない”けれど“どの科にも関係する”この診療科は、複雑な症状を抱える患者に対して、身体・心・生活背景を含めて診断していく専門医です。
松本潤演じる主人公・徳重晃は、まさにこの分野の第一人者として描かれ、従来の医療ドラマとは異なる切り口で物語が展開されていきます。
「患者は、症状そのものではなく“人間”であることを見失わない」
これは、原作漫画でも繰り返し語られるテーマであり、ドラマでも忠実に反映されています。
| 診療科 | 役割 |
| 外科・内科 | 臓器ごと・疾患ごとの専門治療 |
| 総合診療科 | 複数の症状・科をまたぐ診断と治療の司令塔 |
原作の本質を丁寧に再現した脚本と演出
脚本を手掛けるのは、『コウノドリ』シリーズなどを担当した坪田文氏。
彼女の手による脚本は、原作の台詞回しや空気感を損なわずに、映像表現に適した形で巧みにアレンジされています。
とくに患者一人ひとりのエピソードに深く切り込む問診シーンは、脚本と演技、演出のすべてがかみ合って心に迫るものがあります。
また、撮影現場には原作者・富士屋カツヒト氏が訪れ、「実写ならではの情報量が楽しい」と語るほど、キャスト・スタッフの世界観への理解度は高いと評価されました。
「映像化されても、僕のキャラクターは“そのまま生きている”と感じました」(富士屋カツヒト氏)
こうした原作者との強い連携も、原作ファンを安心させる要素のひとつです。
キャストと演技力がリアルな医療現場を再現
ドラマ『19番目のカルテ』が原作ファンや医療ドラマ好きを惹きつける最大の理由は、リアルな医療現場の臨場感にあります。
それを可能にしているのが、松本潤、小芝風花らキャスト陣の説得力ある演技です。
細部まで作り込まれた病院セットと、専門用語を違和感なく使いこなす俳優たちの所作が、現役医師からも「本物に近い」と評価されるほどの完成度を実現しています。
「実際に現場にいるかのような感覚になった」──医療関係者の声
| キャスト | 役柄 | 注目ポイント |
|---|---|---|
| 松本潤 | 徳重晃(総合診療医) | 冷静さと情熱のバランス |
| 小芝風花 | 滝野みずき(研修医) | 成長と葛藤をリアルに表現 |
主演・松本潤が演じる徳重晃の説得力
松本潤が演じる徳重晃は、専門性を超えて「人間」を診る医師としての信念を持った総合診療医。
彼の目線や言葉、そして一歩引いた姿勢には、本当の医師が持つべき倫理観と冷静な判断力が滲み出ています。
特に、患者との対話シーンでは「診断ではなく理解しようとする姿勢」が丁寧に描かれており、原作ファンからも「漫画以上にリアル」との評価が集まっています。
「何も話さなくても伝わる目線の演技に鳥肌が立った」──SNSの反応
滝野みずき役・小芝風花との医療バディ関係
小芝風花が演じる滝野みずきは、整形外科から総合診療科に配属されたばかりの新米医師。
最初は戸惑いながらも、徳重の背中を見て医師としての在り方を模索していく成長ストーリーが展開されます。
松本潤との“医療バディ”としての関係性も物語の大きな魅力。
時には衝突し、時には支え合う関係は、医療現場における「チームでの診療」の重要性を視聴者に訴えかけます。
「理想的な“信頼関係”のモデルとして、多くの研修医に見てほしい関係性」──医療系ライターの分析
原作者・富士屋カツヒトが語るドラマ化の感想
『19番目のカルテ』の原作漫画を手がけた富士屋カツヒト氏は、TBS日曜劇場による実写化にあたって、ドラマの世界観と俳優陣の熱演に深い感銘を受けたと語っています。
彼が感じたのは、「漫画では描ききれなかった情報量」が、実写ならではの演出によって補完され、むしろ読者に新たな気づきを与えてくれるという点でした。
「画面に映る“何も語らない”時間が、逆に雄弁にキャラクターの想いを伝えてくれていました。原作にはなかった“余白”が心地よかったですね。」
──富士屋カツヒト(インタビューより)
| 評価ポイント | 原作者コメント |
|---|---|
| 俳優の演技 | 「役者の表情やしぐさが、言葉以上に深く原作を表現してくれた」 |
| 脚本と構成 | 「話の運び方がとても自然。原作の意図を損なわずにドラマ化されている」 |
| セットと美術 | 「医療の現場感がリアルで、作品世界に没入できる」 |
「実写ならではの情報量が楽しい」と語る理由
富士屋氏は、実写ドラマには“紙面では表現しきれない細部”があると話します。
たとえば、診察室の空気感や患者の表情の変化、スタッフの動線など、視覚と音で感じる空気が、総合診療というテーマをよりリアルに伝えてくれるのです。
ドラマ版では、「診察の一瞬」に込められた登場人物の想いが、無言の演出によって強調され、観る側の想像力をかき立てます。
「実写は“行間”を演じる。そこに新しい気づきがある」──原作者コメントより
撮影現場での原作者とキャストの交流
富士屋氏は撮影現場にも訪れており、主演の松本潤さん、小芝風花さんらキャストと直接交流を持ちました。
その際にキャストから原作へのリスペクトを感じたと話しており、特に松本潤さんからは「医師としての“間”を意識して演じている」との発言が印象的だったそうです。
| 交流したキャスト | 原作者の感想 |
|---|---|
| 松本潤(徳重晃 役) | 「役への理解が深く、キャラの“核”を掴んでいる」 |
| 小芝風花(滝野みずき 役) | 「原作のセリフを研究し、演技に活かしていたのが嬉しかった」 |
現場は終始和やかで、原作者としての意見も真摯に受け止めてくれる環境だったことが語られており、「信頼して任せられる現場だった」と締めくくられています。
原作とドラマの違いを楽しむ視点
『19番目のカルテ』の魅力は、原作漫画とドラマそれぞれのメディア特性を活かした表現の違いにあります。
原作でしか描けない繊細な心理描写と、ドラマだからこそ伝わる空気感。その両方を比較しながら楽しむことで、作品への理解がより深まります。
ここでは、原作ファンだからこそ気づける違いや注目ポイントを紹介します。
「原作の“静”に対して、ドラマは“動”。どちらも違う良さがある」──視聴者の声より
原作コミックとの設定や演出の差異
原作漫画『徳重晃の問診』では、細やかな表情の描写や医師の内面独白が多く、“静かな緊張感”が漂っています。
一方でドラマ版では、同じ場面でも演出のテンポがやや速く、映像的な緊迫感やリアルな音響演出により、別の形で緊張を表現しています。
| 要素 | 原作(漫画) | ドラマ(実写) |
|---|---|---|
| セリフ | 内面を語るモノローグ中心 | 台詞に含まれた行間が強調される |
| 描写 | ペンのタッチで感情を表現 | 表情・声・間で表現 |
| 医療監修 | 専門的な医学情報を文字で提示 | リアルな医療道具と所作で表現 |
読者だからこそ気づけるドラマの工夫
ドラマには、原作にはなかった“視覚的な遊び”や“脚色”がいくつか散りばめられています。
たとえば、徳重が患者を見送る後ろ姿や、滝野の診察前の緊張した手元など、原作に描かれていない“補完のシーン”が数多く存在。
こうした演出は、読者だからこそ「おっ?」と気づける小さな仕掛けであり、作品を二重に楽しむ鍵となっています。
「ドラマには、原作の“裏ページ”がある。そう思わせるカットがあるんです」──SNS読者レビューより
また、セリフの言い回しや構成の順番が一部改編されていることもありますが、それらは実写向けのリズムに最適化された結果。原作の本質を大切にしながら、新たなメッセージ性を与えている点が印象的です。
『19番目のカルテ』ドラマ&原作の魅力を総まとめ
原作漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』とTBS系日曜劇場で放送される実写ドラマ。
この二つのメディアを通して描かれる世界は、医療のリアルと人間の内面に鋭く迫る、まさに“診察を超えた対話”の物語です。
漫画とドラマ、それぞれがもつ特性を活かしたアプローチによって、『19番目のカルテ』という作品はさらに奥行きを増しています。
「診ることは、聞くこと。そして、寄り添うこと。──それがこの物語の真髄です」
漫画と実写の二つのアプローチで広がる世界観
漫画版では、医療現場の緻密な知識をもとに、問診の重要性と医師の“哲学”が丁寧に描かれています。
一方でドラマでは、キャストの演技と映像演出によって、患者と医師の“間”に流れる空気まで体感できるのが特徴。
それぞれの媒体にしかできない表現が、互いの魅力を補完し合っているのです。
| メディア | 表現の特長 | 受け取れるもの |
|---|---|---|
| 漫画 | 心理描写、医療理論の解説 | 医師の思考過程や感情 |
| ドラマ | 視覚と聴覚によるリアリズム | 医師と患者の距離感、感情の機微 |
今後の展開にも注目!医療×人間ドラマの可能性
『19番目のカルテ』の今後の展開で注目すべきは、“病気ではなく人を診る”というテーマが、どのように深堀されていくのかという点です。
徳重晃と滝野みずきが、さまざまな患者と出会い、診断を超えた関係性を築いていく中で、「医療とは何か」「生きるとは何か」という本質的な問いが浮かび上がります。
医療ドラマでありながら、人生そのものに寄り添うヒューマンドラマとしての顔を持つこの作品は、今後の物語の広がりにも大きな期待が寄せられています。
「これはただの医療ドラマじゃない。“人を救うとは何か”を描いた作品です」──視聴者レビューより
この記事のまとめ
- 原作は富士屋カツヒトの医療漫画『徳重晃の問診』
- 松本潤演じる徳重医師の圧巻のリアリズム
- 小芝風花と築く医療バディの成長物語
- 原作と実写で異なる“診る力”の描き方
- 原作者が語る実写ならではの情報量の魅力
- 読者だからこそ気づける細部の演出差
- 映像と原作が補完し合う多層的な世界観
- 医療ドラマにとどまらない“人間ドラマ”の深み

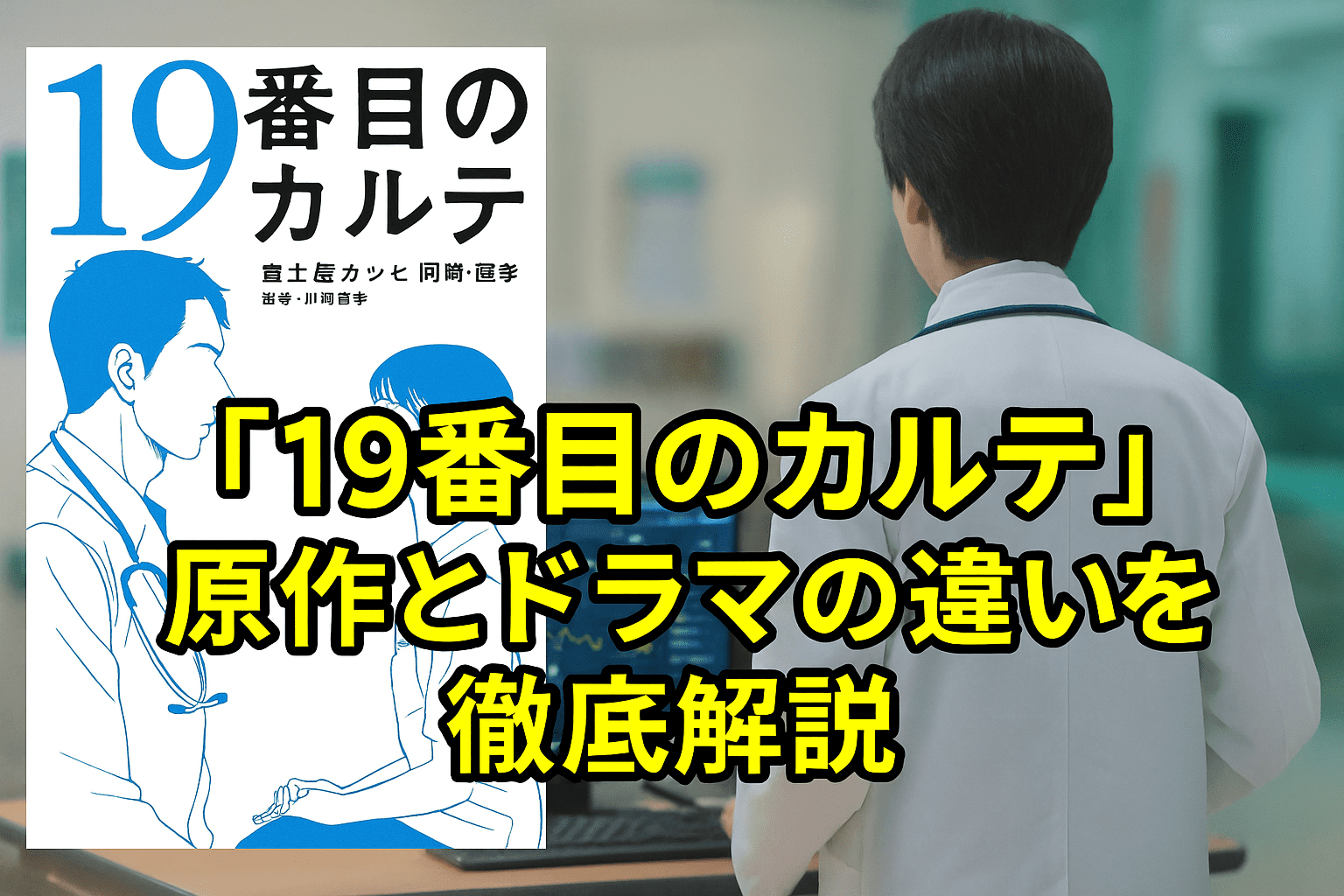
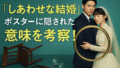
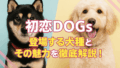
コメント